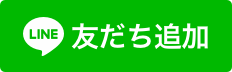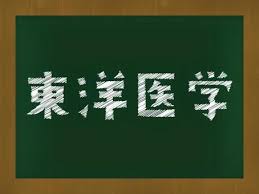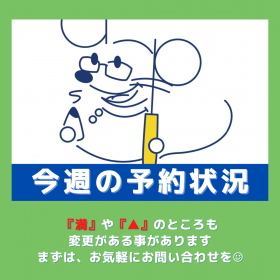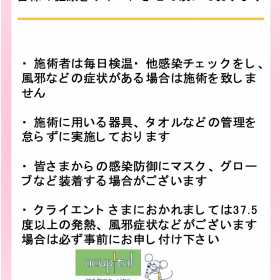【 おからだの悩み 】
☑︎頭痛
☑︎肩痛(五十肩)
☑︎腰痛(ぎっくり腰・坐骨神経痛)
☑︎背中・腕・足の痛み
☑︎自律神経の乱れ
☑︎耳鳴り、難聴
☑︎不眠症
☑︎めまい
☑︎生理痛
☑︎月経前症候群
☑︎むくみ
☑︎便秘
-
【頭痛】
- 頭痛は、頭部や首の周りに痛みを感じる症状で、原因はさまざまです。
緊張型頭痛は、最も一般的な頭痛の種類です。主な原因は、ストレスや疲労、首や肩の筋肉の緊張です。頭全体が締め付けられるような鈍い痛みが特徴で、しばしば軽度から中程度の痛みを伴います。長時間のデスクワークや姿勢の悪さもこの頭痛を引き起こす要因となります。片頭痛は、頭の片側に強いズキズキとした痛みを感じるのが特徴で、吐き気や光・音への過敏を伴うことがあります。ホルモンバランスの変化、ストレス、睡眠不足、特定の食品やアルコールが誘因となることがあります。片頭痛は女性に多い傾向があり、遺伝的な要因も関係しています。
群発頭痛は、目の周りに強烈な痛みを感じる、比較的珍しいタイプの頭痛です。一定期間に集中的に発生し、1日に数回、数週間から数ヶ月にわたり繰り返されます。目の充血や涙、鼻づまりなどを伴うことがあり、男性に多く見られます
-
-
【肩痛(五十肩)】
- 肩痛(五十肩)は、肩関節周辺の筋肉や腱、靭帯に炎症が生じ、肩を動かす際に痛みを感じる状態です。特に50代以降の人に多く見られることから「五十肩」と呼ばれます。主な原因は、肩の使い過ぎや加齢による筋肉や腱の劣化、過度の負荷が原因となることが多いです。また、肩関節周囲の軟部組織が硬くなり、動きが制限されることもあります。
五十肩の症状には、肩を動かすときの痛み、夜間痛、腕の可動域の制限があり、日常生活に支障をきたすことがあります。
-
-
【腰痛(ぎっくり腰・坐骨神経痛)】
- 腰痛は、腰部に痛みを感じる症状で、ぎっくり腰や坐骨神経痛が代表的な例です。
ぎっくり腰は、急激な動きや重いものを持ち上げた際に腰の筋肉や靭帯が損傷し、激しい痛みを引き起こすことです。
座骨神経痛は、腰椎から出る神経が圧迫されて、臀部から太もも、ふくらはぎにかけて痛みやしびれを感じる症状です。腰痛は姿勢の悪さ、筋力の低下、過度の負荷、または椎間板ヘルニアなどの疾患によって引き起こされることが多いです。ぎっくり腰や座骨神経痛の改善には、安静にすることや痛みを和らげるための温冷療法、軽いストレッチやリハビリが有効です。
-
【各種痛み治療(背中・腕・足)】
- 背中や腕、足の痛みは、筋肉や神経、関節などに起因することが多く、生活習慣や姿勢、過度な負荷が原因で発症します。
背中の痛みは、長時間の不良姿勢や過度のストレス、筋肉の緊張が原因となることが一般的です。
腕や足の痛みは、過度な運動や、神経が圧迫されることによって引き起こされることがあります。例えば、腕の痛みは肩や首の筋肉の緊張、手根管症候群や肘部管症候群などが原因となり、足の痛みは坐骨神経痛や膝の関節痛、筋肉の緊張などによって起こります。
-
【自律神経調整】
- 自律神経の乱れは、身体のさまざまな機能を調整する自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが崩れ、体調不良を引き起こす状態です。ストレスや過労、不規則な生活習慣、食事の偏りなどが原因となり、体温調節や血圧、心拍数などに影響を与えます。自律神経の乱れは、疲労感、頭痛、めまい、不眠、食欲不振、動悸など、さまざまな症状として現れることがあります。
-
【耳鳴り、難聴】
- 耳鳴りや難聴は、耳の機能に関する異常で、日常生活に大きな影響を及ぼします。耳鳴りは、外部の音がないにもかかわらず、耳の中で音が聞こえる症状で、原因としては、過度な音の暴露、ストレス、耳の疾患、血行不良、加齢などが考えられます。難聴は、音を聞き取る能力の低下で、加齢や耳の病気、外傷、音の刺激に長時間曝されることが主な原因です。
-
【不眠症】
- 不眠症は、眠れない、または睡眠の質が悪い状態が続くことで、日常生活に支障をきたす症状です。原因としては、ストレス、過労、不規則な生活習慣、カフェインやアルコールの摂取、精神的な問題(うつ病や不安症)などが考えられます。睡眠環境の悪さや身体的な痛みも不眠の原因となることがあります。
-
-
【めまい】
- めまいは、周囲が回っているように感じたり、ふらつきや立ちくらみを感じる症状で、さまざまな原因が考えられます。内耳の異常、血圧の低下、ストレス、貧血、薬の副作用などが主な原因として挙げられます。特に、内耳の問題(例えば、良性発作性頭位めまい症やメニエール病)は、めまいを引き起こす代表的な原因です。
-
-
【生理痛】
- 生理痛は、月経中に腹部や腰、背中などに痛みを感じる症状で、痛みの程度は人によって異なります。主な原因は、月経時に子宮が収縮する際に分泌されるプロスタグランジンというホルモンによるものです。プロスタグランジンの分泌が過剰になると、子宮の収縮が強くなり、痛みが生じます。ストレスや生活習慣、ホルモンバランスの乱れも生理痛を悪化させる要因となります。
-
-
【月経前症候群】
- 月経前症候群(PMS)は、生理の数日前から始まる身体的および精神的な症状で、月経の開始後に改善されることが特徴です。主な症状には、腹部の膨満感、頭痛、胸の張り、イライラ、気分の落ち込み、食欲の変化などがあります。PMSの原因は、ホルモンバランスの変化、特にエストロゲンとプロゲステロンの不均衡が関与しています。また、ストレスや生活習慣、栄養不足が症状を悪化させることもあります。
-
-
【むくみ】
- むくみは、体内に余分な水分が溜まり、手足や顔が膨らんで見える状態です。主な原因には、長時間同じ姿勢でいること、塩分の摂取過多、運動不足、ホルモンバランスの乱れ、血行不良などが挙げられます。特に生理前や妊娠中はホルモンの影響でむくみが現れやすくなります。また、腎臓や心臓、肝臓に関連する病気が原因となることもあります。
-
-
【便秘】
- 便秘は、排便が通常よりも少ない、または困難である状態を指します。原因としては、食物繊維の不足、水分摂取量の減少、運動不足、ストレス、ホルモンバランスの乱れ、薬の副作用などがあります。また、慢性的な便秘は、腸内環境の悪化や生活習慣の影響も関与しています。
-
ご予約・お問い合わせ
メールフォーム
入力間違いにお気をつけください。
問い合わせフォームに入力していただいたメールアドレスや電話番号に折り返しご連絡させていただきますが、入力された情報が違っていた場合、せっかくお問い合わせいただいたのにもかかわらずこちらからご連絡させていただくことができかねます。入力した情報に間違いがないかどうか、ご確認のうえお問い合わせください。
お問い合わせいただいたのに折り返しの連絡が数日間ない場合も入力された情報が違っている場合がございます。
お手数ではございますが、再度ご連絡いただきますようお願い申し上げます。お急ぎの方は電話でお問い合わせください。